紙の出版市場は、いよいよ本格的な崩壊過程に入ったようだ。紙の出版物の売り上げは毎年、前年比で5~10%減少してきたが、今年は10パーセント以上の減少も考えられる状況になっている。
なにしろ、書店の数が激減している。
『出版指標年報2023』によると、2023年3月28日時点の書店総店舗数は1万1149店(前年比457店減)だが、このうち坪あり店舗数は8478店(同328店減)に過ぎないのだ。つまり、いまや、全国のリアル書店数は1万店を割り込んでいて、これはピーク時の1960年の2万6000店の3分の1ということ。
しかも、今後も閉店数は増え続ける。この6月の書店閉店数は62店で、大型店ではTSUTAYAの7店、西友の9店が目立つ。
いまや、大型店、スーパーやショッピングモール内の書店も存続できない状況になっている。そんなか、書協の会員社の近刊情報誌『これから出る本』(月2回刊)は、12月下期号で休刊(廃刊)することをすでに決めている。
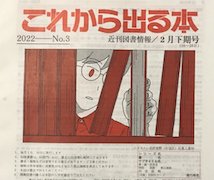 休刊で40年の歴史に幕
休刊で40年の歴史に幕
それでも、なんとか書店を続けようと、日販は商業施設などの空間づくりを行う㈱丹青社と連携し、東京メトロ溜池山王駅(東京・千代田区)に無人書店「ほんたす ためいけ 溜池山王メトロピア店」をオープンする。これは、果たして書店というビジネス形態が持続可能かどうかの実証実験である。「日常に本の楽しみを! フラっと、サクっと旬を手に」をコンセプトに、街ごとの顧客にとっての旬のテーマに特化した品揃えで商品展開するというが、果たしてどうなるのか?